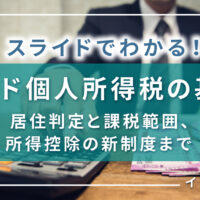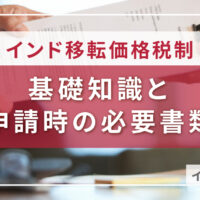本記事では、コロナ禍におけるインド駐在員に起き得る所得税の範囲の変更と課税リスクについて解説していきます。
現在、コロナウイルスの感染拡大により、多くの方が2020年3月末のロックダウンを機に帰国しており、2020年4月1日からは1日もインドに滞在していない状態の方が増えています。これによりインド側の居住ステータスが変更となる可能性があり、それに伴う、課税範囲の変更や課税リスクが起こり得ます。
日本での滞在が長期化している方以外にもこんな方は、ご一読ください。
・平常時は、インドに居住し、インド子会社の業務に従事しながら、日本本社からの日本払い給与と、インド子会社からのインド払い給与の2つを受け取っている
・平常時は、インドに滞在し、インド会社の業務のみに従事、給与もインド払いのみだが、日本への長期出張がある
-
-
- インド駐在員の日本一時帰国に伴う日本側のルールから課税リスクを考える
1-1. 日本の居住判定の方法
1-2. 日本への長期一時帰国に起き得る3つの課税リスク
① 駐在員のインド払い給与が日本での総合課税対象となるリスク
② 日本PE認定となった場合の課税リスク
③ 帰国中の駐在員が日本本社業務も行う場合の課税リスク - インド駐在員の日本一時帰国に伴うインド側のルールから課税リスクを考える
2-1. インドの居住判定の方法(事例:2020年3月31日までに日本へ帰国した駐在員の方)
① 通常の居住者の課税対象と課税リスク
② 非通常の居住者の課税対象と課税リスク
③ インド非居住者に該当する場合の課税リスク - ケーススタディと課税リスク回避のための手段
① 日本が居住者で、インドが非居住者と判定される場合
② 日本が非居住者で、インドが居住者と判定される場合
- インド駐在員の日本一時帰国に伴う日本側のルールから課税リスクを考える
-
本件をご理解いただくためには、日本側およびインド側の所得税及び居住判定におけるルールの両側面から理解する必要があります。

インド駐在員の日本一時帰国に伴う日本側のルールから課税リスクを考える
まず日本で課税される所得税の課税範囲ですが、こちらは日本の居住者であるか、非居住であるかによって変わってきます。日本の居住判定についてご説明し、居住者判定別の課税範囲ついてお伝えしていきます。

日本の居住者判定の方法
日本の居住者、非居住者の定義は以下の通りです。
| 居住者 | 非居住者 |
| 国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 | 居住者以外の個人 |
※住所とは、個人の生活の本拠
※居所とは、その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所
生活の本拠かどうかは、客観的事実によって判定することになります。ここでいう客観的事実とは、例えばその個人の資産の所在、職業、親族等の情報に基づきます。日本国内法では、インドのように日本の滞在日数や住民票の有無だけでは、居住者・非居住の判定を行っていません。
上記を踏まえた上で、長期帰国時に起こり得る課税リスクについて解説していきます。
日本への長期一時帰国に起き得る3つの課税リスク
一時帰国が長期化している駐在員の方に起き得る以下3つのパターンについて解説します。
- 駐在員のインド払い給与が日本での総合課税対象となるリスク
- 日本PE認定となった場合の課税リスク
- 帰国中の駐在員が日本本社業務も行う場合の課税リスク
①駐在員のインド払い給与が日本での総合課税対象となるリスク
平常時、インド居住者としてインドに駐在し、インド払いの給与を受け取る場合は、日本払い給与も含めてインドで課税される為、日本では源泉徴収されません(日本での所得税課税無し)。
しかし、短期、長期に関わらず一時帰国に伴い日本で勤務を行っている駐在員には課税リスクがある事をご理解下さい。

例えば、上記図の通りインド駐在の時と同じようにインド払給与、日本払給与を貰っていながら一時帰国を行っているケースです。
まずは、ご自身が日本居住、非居住どちらに該当するかを明確にしたうえで、下記の図から課税対象をご判断ください。
| 居住区分 | 課税対象 |
| 居住者 (インド非居住者) | 全世界所得課税 インド払給与も日本で総合課税 |
| 非居住者 (インド居住者) | 国内源泉所得(日本払・インド払)は課税 日本払い給与:日本本社は源泉徴収義務 インド払い給与:確定申告義務※短期滞在者免税規定あり |
ここで抑えておきたいポイントは、日本の居住者であっても、非居住者であっても、日本国内にて勤務している場合には日本で課税されるという事です。
日本の非居住者で、インド払給与を受け取っている場合には、短期滞在者免税という制度が使用できるのでこちらも併せてご確認下さい。
これは、日本国内においてインド会社の業務をしている場合も同じです。日本の国内勤務に起因して発生している給与なので、例えインドの仕事をしていてインド会社から受け取った給与であっても日本で課税が必要なので、注意してください。
②日本でPE認定となった場合の課税リスク
PEとは、Permanent Establishmentの略称で、「恒久的施設」と呼ばれます(※1)
日本への一時帰国が長期化し、日本でPE認定された場合には、日本での帰属所得の計算、申告納税が必要となります。
日本かインド、いずれの国でPE認定をうけるかの判断は、駐在員にとって誰が真の雇用者であるかという点が判断指針となります。インドで通常業務に従事している限りは、基本インド企業が真の雇用者とみなされますが、駐在員の日本一時帰国が長期化し、インド子会社の業務を日本で行う状態が続くことで、日本本社が真の雇用者とみなされた場合は、日本のPE認定リスクが高まります。
なお、令和2年4月3日、OECDより新型コロナウイルスによる一時的な居住地の異動に伴い生じるPE認定については、例外的にPE認定を控えるように考慮すべきというコメントが発表されています。
※1 PE (Permanent Establishment): 日本語で「恒久的施設」と呼ばれます。 非居住者および外国法人に属する駐在員がインド(非居住国)で事業を行う場合でも、インド(非居住国内)にPE(恒久的施設) を有していない場合、その駐在員(非居住者)および外国法人の事業所得は居住国である日本で課税されるという考え方です。
国際取引の場合、その所得に対して法人の居住国が課税するか、ビジネスが行われた国が課税するかが論点となりますが、その時「PE(恒久的施設)なければ課税なし」という考え方が適応されます。
「PE(恒久的施設)なければ課税なし」とは、原則として日本国内にその企業のPEがなければ、その企業の事業利得に課税できません。 また、日本企業が海外に進出した場合にも、PEと認定されなければ、進出先国で課税されることはありません。
③帰国中の駐在員が日本本社業務も行う場合
最後に、帰国中の駐在員がインド子会社業務も日本本社業務も行う場合の課税リスクについてです。
こちらのケースにおいても、ご自身が日本居住、非居住どちらに該当するかを明確にしたうえで、下記の図から課税対象をご判断ください。
| 居住区分 | 課税対象 |
| 居住者 (インド非居住者) | 全世界所得課税 インド払給与も日本で総合課税 |
| 非居住者 (インド居住者) | 国内源泉所得(日本払・インド払)は課税 日本払い給与:日本本社は源泉徴収義務 インド払い給与:確定申告義務※短期滞在者免税規定あり |
インド子会社の業務と、日本本社の業務に従事する場合は、インド出向中の駐在員が日本本社業務に従事する形となる為、インド子会社から日本本社への役務提供があると捉えられるリスクがある事を認識する必要があります。
対応方法としては、インド子会社と新たな契約を結びインド法人に一定の費用を支払う等が挙げられます。

インド駐在員の一時帰国に伴うインド側のルールから考える課税リスクとは
インド側の居住判定を理解していただいた上で、居住者判定別の課税リスクについてお伝えしていきます。
インドの居住判定の方法
日本に長期帰国をしている方は、インドにおける居住判定が納税義務の課税リスクを検討するにあたり一番の肝になります。以下のスライドをご覧ください。

駐在員の方は自分自身が
①通常の居住者 ②非通常の居住者 ③非居住者
いずれのステータスに該当するか、海外子会社管理されている方は自社の帰国している駐在員はどのステータスに該当するかを確認します。

・過去4年でインドでの滞在期間が365日を超えていれば、2021年3月31日までにあと60日インドに滞在すれば居住者と判定されます。
・過去4年で365日滞在していなければ、2021年3月31日までにあと182日インドに滞在しなければ居住者と判定されません。つまり、非居住者と判定されます。
ご自身の居住区分が分かると、課税範囲も以下の通り明確になります。
| 通常の居住者 | 全世界所得(インドの所得、日本の所得など) |
| 非通常の居住者 | インド国内で受け取ったあるいは発生した所得、インドで関わっている活動から発生している所得で、インド国外で発生し受け取る所得 |
| 非居住者 | インド国内で受け取ったあるいは発生した所得 |
ご自身のステータスはご自身でしっかりと管理するようにしてください。日数要件は海外出張だけでなく、プライベートの旅行での出国等も含まれますので、必ずインドでの滞在日数のカウント、現在の居住ステータスをご自身で管理の上把握頂ければと思います。
ここからは、状況別の課税リスクについてみていきます。今回は、以下3つについて取り上げます。
① 通常の居住者に該当する場合の課税リスク
通常の居住者に該当した場合は、以下の課税範囲・および課税リスクが考えられます。
| インド所得税の課税範囲 | 全世界所得課税 |
| インドで必要な申告所得 | 日本本社からの給与/インド法人からの給与/賃貸住宅貸与/自動車貸与/所得税手当/その他日本で受け取っている給与以外の所得もインドで申告が必要となります。 |
注意すべきリスク
・日本とインドの両国で源泉税の納付が必要となる
・インド側での外国税額控除(インド税務当局の返金時期や金額に対する不安定さ)
② 非通常の居住者に該当する場合の課税リスク
非通常の居住者に該当した場合は、以下の課税範囲・および課税リスクが考えられます。
| インド所得税の課税範囲 | インド国内で受け取ったあるいは発生した所得、インドで関わっている活動から発生している所得で、インド国外で発生し受け取る所得も含む |
| インドで必要な申告所得 | 日本本社からの給与(※)/インド法人からの給与/賃貸住宅貸与/自動車貸与/所得税手当/など |
※原則、日本本社から直接受け取る給与の内、日本本社の業務に従事している対価は該当しない
注意すべきリスク
・一定期間日本とインドの両国で源泉税の納付が必要となる
・インド側での外国税額控除(インド税務当局の返金時期や金額に対する不安定さ)
③ インド非居住者に該当する場合の課税リスク
インド非居住者に該当した場合は、以下の課税範囲・および課税リスクが考えられます。
| インド所得税の課税範囲 | インド国内で受け取ったあるいは発生した所得 |
| インドで必要な申告所得 | インド法人からの給与/賃貸住宅貸与/自動車貸与/所得税手当/など |
※日本本社からの支払い給与もインド法人に請求してインド法人負担としている場合は該当
注意すべきリスク
・インドで課税が必要な所得がある場合は二重で源泉税が徴収される
・非居住者としてインド所得だけを課税していた後に、居住者ステータスとなった場合の非居住者期間過少納税扱いのリスク

ケーススタディと課税リスク回避のための手段
最後に、考えられる主なケースを2つ上げてリスク回避のための考えられる方法をまとめます。
日本が居住者で、インドが非居住者の場合
この場合、駐在員に帰任辞令を出し、インド駐在員から本社所属に異動させましょう。可能であれば、インド側での給与や手当を止め、下記のリスクを回避しましょう。
※インド側で給与や所得が発生しないため、インドで源泉徴収が不要となります
注意すべきリスク
・ITCC(納税証明書)を取得していない帰任のため、ビザ等の手続きでトラブルとなる可能性があること
・帰任後もインド法人の業務に従事する場合、日本法人とインド法人の間で役務提供の論点があること(PE課税のリスク)
通常、インド側での帰任が決まると納税証明書を取得し、出国の際に空港で提示するのが本来の正しい手順とされていますが、今回のコロナ禍のまま帰任扱いとした場合には、これらの対応を省略しているという事だけご認識下さい。
※現時点で確認している範囲では、大きなリスクとはならないと思われますが、念のため記載させて頂きます
日本が非居住者で、インドが居住者の場合
この場合、海外駐在員の一時帰国者として、日本では非居住者として取り扱いましょう。
※帰任辞令等の対応や、日本法人とインド法人間での役務提供の論点については考慮不要です
※インドでのビザ基準給与等の条件に対応してください
注意すべきリスク
・インドでの外国税額控除の適用における不安定さがあること
・日本とインド両国での源泉税徴収の可能性があること
・緊急状況下でのスケジュールによってはインドの居住者要件を満たせない場合があること
今までの駐在員一時帰国とは異なり、駐在員が長期帰国するケースとなった今回のコロナ禍では、駐在員が日本滞在する事におけるリスクと対応に置いて非常に多くの混乱を生みました。しかし、今まで方針を整備していなかった多くの会社が、本来のルールの理解と把握、そしてリスクと実務的対応に関して考える機会にもなったとも考えられます。
本記事にて記載させて頂きました通り、この論点に関しては多くの視点から考慮検討する必要があり、とても個別ケースが大きい内容となります。今後同じような状況が発生した場合に、スムーズに対応出来るよう、本記事の内容を把握して事前にルールを整備いただければ幸いです。 ご不明な点等御座いましたら、お気軽にご相談ください。

◆古東 翔二朗(インド法人責任者)
税理士法人日本経営(現 日本経営ウィル税理士法人)に入社後、主に税務顧問・財務コンサルティング業務に従事し、2016年よりタイの提携事務所に2年間出向。日系企業の進出支援や記帳代行サービス、保険業務の日本人コーディネーター業務を行う。 2018年11月よりインド(デリー/グルガオン)へ赴任。
【免責事項】
本記事でご提供するアドバイス及び情報等は、記事作成時点で私どもが把握している事実及び情報、法律等に基づいています。また、本記事内でご紹介させていただいた内容のうち、法律・制度に関するものは、一般的な内容を分かりやすく解説したものです。貴殿の実行及び意思決定等につきまして、弊社は助言の範囲を超えるものではないことをあらかじめご了承ください。